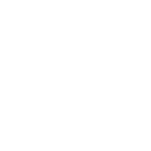筆者自身が中学2年生の時でした。
両足の膝から下が湿潤な湿疹ができてとてもかゆく、かいたところから透き通った体液が出てきてそれが固まり、歩くたびにひび割れて痛くなる何とも困った状態になったことがあります。
伸縮性の肌色の包帯を巻いてそのうえからハイソックスをはいてはた目からはなんともない状態に保っていました。
母はフルタイムで働き、父は闘病中だったので家族は私の窮状には気づいていなかったと思います。
どうしてこんなことになったのか、一人悶々としていた時に当時の親友が「いつからそうなっちゃったの?」「学年が始まったときはハイソックスをはいていなかったよ」と記憶をたどる時間に付き合ってくれました。
それで解明できたことは、6年生から猫を飼い始めとてもなついて、学校から帰宅してからはずっと猫が私の足の間を行ったり来たりして、体を摺り寄せてくることがきっかけになっているのではないかということでした。
飼ってから1年間は何も起こらなかったのに、気づいた時にはとても大変なことになっていました。
猫は父のそばには近寄らず、ほかの家族には平等になついていたと思います。
でも家族の中で一番長く接していたのは私だったと思います。
親友と語り合ううちに、6年生の後半から小さい頃ひどかった喘息が少しぶり返しているような気がしていたことを思い出しました。
中学生になってからは、鼻水が止まらずティッシュなしではいられなくなっていたことに思い至りました。
両親は、喘息のある子は大きくなったら鼻炎が出てくる子が多いらしいよと言って私を慰めていました。
膝から下のピンチが母の知るところとなったのは、2年生の夏にプールに入ることができないほどひどくなったからでした。
「プールを見学したいので保護者のサインがほしい」と言うとその理由を追及されました。
包帯をはずそうにも布が皮膚に張り付いてはがれなくて、母に見せようとしたときには浸出液で包帯が固まってコルセットのようになっていました。
母の手際は完璧でした。
お風呂場でお湯に溶かすようにして包帯を外し、シッカロールで真っ白になるまで足をパタパタはたいて、炎症を抑える漢方薬の軟膏(紫色の匂いが強い薬でした)を塗って、何も覆わずに数週間を費やしたと思います。
たぶん最初の何日かをずる休みして、土日を駆使してできるだけ家に閉じこもり、においの強い薬は学校に行く日は使わず、だましすかししながら夏休みに入ると、また紫のくすりを塗りたくり、夏が終わる頃にはまあまあの状態に落ち着きました。
困ったことに、紫色の匂いのする薬を塗っている間は、猫は遠巻きにして私を見ているだけでしたが、薬を塗らなくなると猫がまた体を摺り寄せてくるようになりました。
肌が治ってから猫に触れると明らかに傷口が増えていくのがわかりました。
そんなことをふた夏繰り返してようやく家族みんなが同じ認識を持つようになり、猫をどうすべきか家族で話し合うことになりました。
ずいぶん前のことなので詳細は忘れてしまいましたが、猫の行く末を私が決めてよいという結論だったと思います。
本当は猫の貰い手を探すつもりでいたのですが、そんな話し合いをしている最中に猫が近所の野良猫とけんかして瀕死の重傷を負ってしまいました。
父は闘病中、母はしゃにむに働いて4人家族の暮らしを支えていたので、当時でも数万円する猫の治療費を捻出してほしいなどとは言えませんでした。
猫をタオルでくるみ籐製のバスケットに入れて、バスで30分行ったところにある保健所をひとりで尋ねました。
その時の私の姿はひざ下が包帯でぐるぐる巻きになっていて、両肘にも包帯を巻いていました。
保健所の人は親切で「バスケットは受け取れないんですよ」といってタオルでくるまれた猫を捧げ持つようにして受け取ってくれました。
私は大好きな猫よりも自分を選んだのです。
そしてそれきり動物を飼うことはありませんでした。